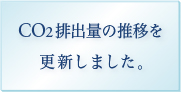| ●かわら版 | ||||||||||
| リコー沼津事業所 | ||||||||||
2006年3月3日 | ||||||||||
|
1. 始めに 2006年3月3日、電気硝子工業会主催の株式会社リコー沼津事業所見学会に参加させていただきました。私は入社以来5年間、ISOと5Sの事務局という立場で、これらの仕事に関わってきました。ISOや5Sは全社員を対象としているため、管理職から現場の作業者に至るまでその考え方を浸透させ、当社で定めたルール通りに実行してもらわなければなりません。しかし、現実はなかなか難しく、常日頃から、他社の管理状況にとても興味を持っていました。今回は、工場での環境保全活動,TPM活動,目で見る管理などを見学ISO14001の認証を取得したばかりなので、事業所から出るごみの分別処理についても興味があり、今後、当社においても分別を実施していく上で何か参考にできるものがあればと思い、参加しました。 |
||||||||||
|
2. リコー沼津事業所概要 創業は1960年。事業内容は、情報機器関連サプライの研究・開発・生産です。事業所は、北プラントと南プラントに別れており、北プラントの敷地面積は約1万3千坪、南プラントの敷地面積は約2万3千坪で、合計すると東京ドーム3.5個分に相当するそうです。 沼津事業所で主に生産されているものは、ジェルジェットプリンターIPSiO(イプシオ)に使われているインク(ジェルジェットカートリッジ),有機光半導体,乾式トナー,ジアゾ感光紙,サーマルペーパー(POSラベル),熱転写リボン,カードアプリケーション等があります。 |
||||||||||
|
3. サーマル工場見学 サーマル工場では、TPM活動や5S活動、目で見る管理等について、説明していただきました。 (1) TPM活動 TPM活動では、大きく4つのテーマが取り上げられていました。1つ目は、モニタリング活動。品質バラツキの定量化を図り、品質のバラツキの小さい製造条件の確立を目指していました。2つ目は、不良品を作らない活動。誰が作業しても同じ品質が得られるように写真入りの作業手順書を活用していました。これは新人教育の効率化にもつながり、とても実用的なものとなっていました。3つ目は、時間稼働率向上活動。段取り時間の極小化を目指していました。4つ目は、性能稼働率向上活動。広幅化・高速化を目指していました。これら4つを総合的に評価する手段として、設備総合効率というものを活用していました。設備総合効率は、良品率×時間稼働率×性能稼働率で計算されていました。これらの活動を通して、必要最低限の材料・設備で品質の良い製品を低コストで製造していくということを確実に実施されていました。 今後、製造業として生き残るためには、この設備総合効率という考え方がとても重要な課題になってくると思います。 (2) 5S活動 5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)+3S(しっかり・しつこく・信じて)の8Sで活動が行われていました。 工場内の通路は、作業スペースや置場スペースと区画線できとんと区別されていました。また、通路は赤色,作業スペース・置場スペースは緑色というように塗り分けられていました。大抵は、時間が経つにつれて色が剥がれてくる箇所が出てきますが、沼津事業所では、大規模な塗り替えは年一回で、あとは日々のメンテナンスで対応しているということでした。実際に、工場見学中もペンキが剥がれている所は見当たらず、徹底して行われている様子がうかがえました。 工具類は、一つ一つ工具の形にかたどった置場を用意してあり、使用した後は必ず同じ場所に戻せるようになっていました。また、各自の名札が用意してあり、それを持出した工具置場の画鋲に掛けることにより、持出した人が一目でわかるようになっていました。これらも乱れることなく、きちんと維持されていました(写真1)。 また、材料などには発注点管理というものを導入していました。これは、生産に使用するための必要最低限の在庫しか持たないようにして、頼みすぎによるムダな在庫やムダな置場スペースの発生を防止するための効果的な方法になっていました。 |
||||||||||
|
||||||||||
|
4. 中央リサイクル市場見学 (1) テーマパーク テーマパークにおいては、ごみゼロ工場達成までの道のりを説明していただきました。その内容は以下の通りです。 1:各部署単位にて廃棄物調査を実施 どこの部署のどの工程からどのような廃棄物がどれくらいの量発生するのかを記入できる「調査カード」を作成し、それを現物に貼付け、実態を調査。 2:リサイクルルートの確立 事業所から出る全ての廃棄物について、メーカーへ問い合わせをしたり、新聞雑誌等からリサイクル技術情報を収集したり、産業廃棄物展へ出かけること等により、リサイクルルートを構築。 3:ごみを買わない工夫 全ての購入原材料の包装・梱包等について、6つのキーワードをもとに、仕入れ先とアイデアを出し合って、無駄な廃棄物を削減し、コストダウンを図る。 【キーワード】 ●そのまま使用できないか ●無駄な包装はないか (例:ダンボールに入っている紙テープの個別包装を無くす) ●小さい容器から大きな容器へ (例:20kg入りの紙袋から400kg入りのフレコンに変更) ●リサイクルしやすい材質への変更 ●材質の統一化はできないか ●再資源化できないか 4:それぞれの廃棄物の再生品を展示 テーマパークにどの廃棄物がどんなリサイクル品になるのかを展示することにより、リサイクルの状況が一目でわかるようにする。 ここでは、棚は3段に分けられ、下段には事業所から排出される廃棄物(例:各種ガラス類)、中段には、その廃棄物の中間処理の状態(例:ガラスを砕いたものと埋立焼却灰を混ぜたもの(溶融スラグ))、上段には、再生品(例:溶融スラグを3%配合の透水性ブロック,溶融スラグを原料とした陶器,溶融スラグを塗料化した自動車用ウッドパネル)が飾られていました。(写真3) ここでは、分別排出のルールについて、現物を実際見ながら学ぶ教育が行われているそうです。 |
||||||||||

|
||||||||||
写真3
|
||||||||||
|
5:リサイクル品の種類の減少 廃棄物の行き着く所は、リサイクル品であり、この種類をなるべく少なくすることが、分別の種類を少なくすることにつながる。 現在、沼津事業所では3120種類の廃棄物を56分類のリサイクルルートにのせて、分別を行っている。 6:分別処理の徹底 分別はリサイクル活動の要であるが、各部署の理解と協力、そして無理のない分別方法が必要となる。そのため、分別を楽しくするため、「遊び心を取り入れた分別ステーション」を設置する等、社員の意識改革を行った。 テーマパークには、上記のような一連の活動内容が一目でわかるように展示されており、 様々な苦労と工夫を見ることができました。 (2) 中央リサイクル市場 各職場で分別された56分類の廃棄物の内、共通で排出される26分類の品が、この中央リサイクル市場に集められています。場所は、事業所の敷地の真ん中にありました。どの職場からも排出しやすいといった利点はもちろんですが、一番の効果は誰もが目に付く所に廃棄物置場を設置することで、きれいで清潔に保つことができるそうです。実際、リサイクル市場の中を見学しても、廃棄物置場といった印象はまったく受けずに、これからリサイクルされるための品物の倉庫のような雰囲気でした。入り口には、写真4のようなレイアウト図があり、廃棄する場所が一目でわかるようになっていました。 リサイクル市場内の各エリアには、シャッターがあります。これも廃棄物置場をきれいに保つ工夫の一つで、ごみを排出する時間帯(例えば、12:30~15:30)が決められており、それ以外はシャッターを閉めているそうです。また、ごみを排出する時間帯には、リサイクル市場の管理者がいて、分別状況をチェックしているため、間違った分別をしない・できないような仕組みになっていました。各エリアには、写真5のようにユニークな名前が付けられています。ダンボール,雑誌・カタログ等の置場には「ブックランド沼津」、ガラス類,蛍光灯等の置場には「BARクリスタル」というようなものです。単なるごみ置場といった観念をなくし、廃棄物を捨てることも楽しくできるようにという目的で導入されたそうです。こういう遊び心を持つことが従業員の協力を得るためには、必要であると感じました。 |
||||||||||
|
||||||||||
|
また、中央リサイクル市場は単なる集積場所としての機能だけではありませんでした。持ち込んだごみをさらに分解できるように解体作業道具が置かれていて、この場所で作業ができるようになっていました。プラスチックは、減容機を使用して体積比で1/30~1/50まで減容できるようになっていました。さらに、計量機がおいてあり、各部署から出る廃棄物の量はそこで計量し、各部署所有のカードに記録させていました。その記録を活用して、処理費用を排出元で負担する仕組みが取られていました。このようにすると、どの部署も積極的に排出量の削減に努めるそうです。各部署で不要になった事務用品等を展示し、必要な部署で再利用するためのコーナーも設けてありました。 (3) 省資源・リサイクル活動 環境負荷低減のための活動として、次の5つのRで展開されていました。 1:リフューズ(Refuse):不要な資源や製品は購入しない。 2:リターン(Return):再使用、再生利用できるものは購入先や回収業者に返す。 3:リデュース(Reduce):資源や製品の使用量、廃棄物量の発生量を極力抑える。 4:リユース(Reuse):繰り返し使用できるものは再使用する。 5:リサイクル(Recycle):廃棄物は極力再資源化し、循環利用する。 一般的に知られている3R(Reduce,Reuse,Recycle)に2つのRが付け加えられていて、それぞれの活動内容がより具体化されていて、理解しやすくなっていました。 |
||||||||||
|
5. 地域住民とのコミュニケーション 地域住民の方の率直な意見をもらえるようにSSモニター制度(SS=Social Satisfaction 社会的満足)というものが導入されていました。これは、近隣の地域からモニターを選出し、年2回アンケートに協力してもらうという方法で行われています。良い評価から厳しい評価まで、生の意見が得られるそうで効果的に運用されていました。今後は、大企業はもちろん、中小企業においてもこのような環境における社会的満足度の向上がますます重要になってくると思います。 |
||||||||||
|
6. 終わりに この見学会を通じて、多くの知識を得ることができました。特に、ごみゼロ工場に向けての活動内容は、ユニークかつ無理のないものになっており、今後の当社における環境活動にとても参考になるものでした。また、TPM活動、5S活動、労働安全衛生活動等、様々な活動が独立しないで、お互いに関わりを持った活動内容になっていて、すべての活動が経営の役に立つものになっている印象を受けました。 今回このような機会を与えていただきました、株式会社リコー沼津事業所様と電気硝子工業会様に御礼申し上げます。 |
||||||||||

|
||||||||||
| 岡本硝子株式会社 品質保証室 ISO推進課 サブリーダー 櫻井 健一 |
||||||||||